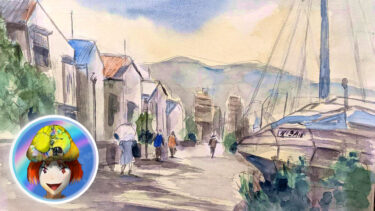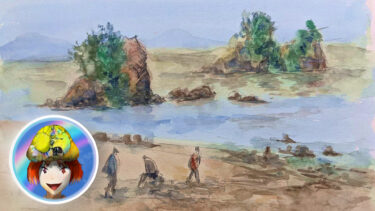今回はホーホケキョで有名な、ウグイスについてです。
美しい鳴き声に隠された真剣な表情や、変わった結婚制度、名前の由来などについて述べますので、良かったら読んでみて下さい。
ウグイスとは

ウグイス(ウグイス科)Cettia diphoneは、全長♀14cm、♂16cmでスズメと同大かやや大きい小鳥です。
留鳥または漂鳥として平地から亜高山帯まで、林縁や藪に棲みます。
徳島県の剣山(標高1955m)でも、夏季は山頂付近まで普通に観られます。
ウグイスの結婚制度
・佐那河内村大川原高原.jpg)
ウグイスの体はオスの方がメスより一回り以上大きいです。
この場合、動物の世界では「一夫多妻」のことが多いようです。
ウグイスも例にもれず、雄の縄張りに、複数のメスを囲います。
多い時は7羽ものメスを囲います。そして、巣作りや子育てはもっぱらメスに任せて、オスは毎日、囀ってばかりです。
しかし、メスの方もしたたかです。
一回目の子育てが終わると、別のオスの縄張りへ入ってそちらのオスと再婚し、2回目の子育てをします。
こういうのを、「連続的一妻多夫」とも呼びます。
日本の三鳴鳥

ウグイスのオスはきれいな、そして大きな声でよく囀ります。
それで、古来、オオルリ、コマドリと並んで、「日本の三鳴鳥」にかぞえられてきました。
囀る時の姿をよく見ると、その熱意と真剣さが伝わってきます。
喉を大きく膨らませ、そのピンクの地肌を丸出しにしてなりふり構わず「ホーホケキョ」と一所懸命囀ります。
(喉の皮膚が透けてる)・大川原高原-e1624686300775.jpg)
(喉の皮膚がむき出しに)佐那河内村大西-e1624686339820.jpg)
因みに、徳島県では2月28日ごろから、8月15日ごろまで囀りがきかれます。
日本三鳴鳥、ウグイスの鳴き声の動画
日本三鳴鳥、オオルリの鳴き声の動画
日本三鳴鳥、コマドリの鳴き声の動画
ウグイスの名前の由来

古来、日本人に親しまれてきたウグイスですが、その名前の由来については定説がないようです。
『動物名の由来』(注1)では、貝原益軒(1630~1714)著『日本釈名』(注2)の解釈に沿って「ウグイスとは“奥出ず”の意味となる。私はこの説明が一番当たっているように思える」としています。
確かにウグイスはたいてい藪の奥にいて容易に姿を見せないし、「奥出ず⇒オクイズ」と発声すれば「ウグイス」とも聞こえます。
(注1)中村 浩(1981)『動物名の由来』 (東京書籍)
(注2)日本釈名 3巻 - 国立国会図書館デジタルコレクション
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2605377
チチクラゲの新説!ウグイスの名前の由来
.jpg)

なぜなら、ウグイスといえばその囀りにこそ特徴があると思うからです。
個性の強い独特のメロディーと音色は誰の耳にも印象深いはずです。
従ってこの鳥の名前はさえずりに因んで名づけられたと考えるのがごく自然であると思います。
その手がかりになるのが古代日本語の発音です。
「は行」をパ、ピ、プ、ペ、ポのように、
「さ行」をツァ、ツィ、ツ、ツェ、ツォのように発音していたといわれます。
この音で「うくひす」を発音してみると、「ウクピツ」となります。
さらに「ウ」を少し伸ばすと「ウークピツ」となり、ウグイスのさえずりにかなり近づきます。
古今和歌集に
「心から花のしずくにそぼちつつ うくひすとのみ鳥の鳴くらん」
があります。
また、承暦二年(1078年)内裏歌合にも
「いかなれば春来る毎にうぐひすの己の名をば人に告ぐらん」
など、ウグイスが自分の名を鳴いていると詠んだ歌があります。

まとめ
ウグイスについてのまとめです。
- 全長14-16cmでスズメと同大かやや大きい小鳥で、林縁や藪に棲む。
- 一夫多妻制度や、連続的一妻多夫制度を採用。
- 日本三鳴鳥の一種。喉を大きく膨らませ、ピンクの地肌を見せて「ホーホケキョ」と精一杯鳴く。
- 名前の由来:藪の奥にいて容易に姿を見せないため、「奥出ず⇒オクイズ」と呼ばれ、「ウグイス」となった。
- チチクラゲが唱える名前の由来の新説:ウグイスのさえずりから取った。
次回はゴイサギです。

ロゴ.png)