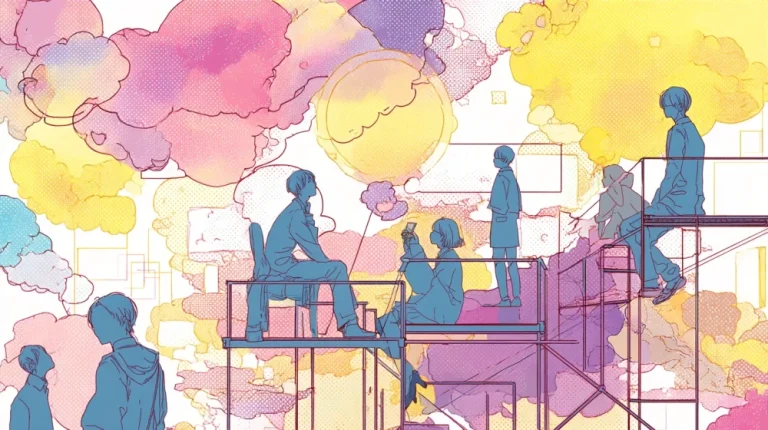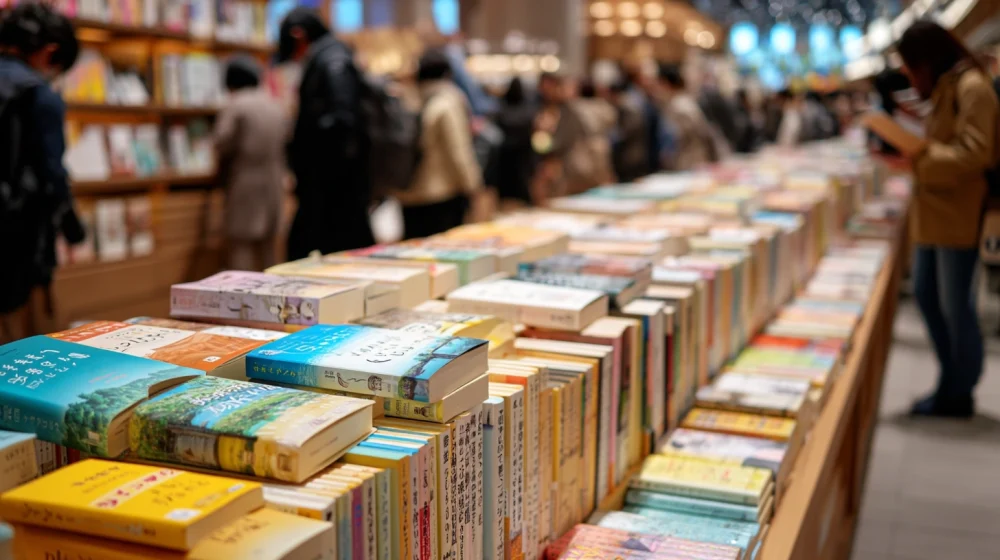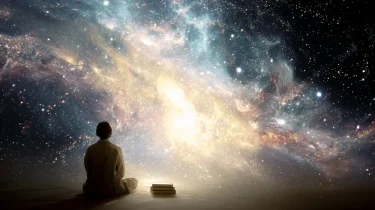アドラー心理学は、一人の天才が遺した理論で止まることなく、100年以上にわたって進化し続けています。
創始者アルフレッド・アドラーの死後も、弟子たちが思想を引き継ぎ、時代の流れと共に理論と技法を現代化させてきました。
本記事では、アドラー心理学がどのように継承され、広まり、変化してきたのか、その歴史と人物たちにスポットを当てて紹介します。
時代や思想が変わっても色あせないアドラーの哲学。その進化の歩みをたどってみましょう。
原典主義にとらわれないアドラー心理学の特異性
多くの思想体系は創始者の言葉を「絶対」として保存しようとしますが、アドラー心理学は違います。
アドラーの理論は、彼の死後も積極的に再構成・発展され、「生きた心理学」として柔軟に成長してきました。
アドラーが1937年に亡くなった後、第二次世界大戦とナチスの迫害によって、彼の多くの弟子たちは命を落としたり、散り散りになってしまいます。
こうした混乱の中で、「アドラー心理学はもう終わった」とさえ囁かれる時期もあったのです。
それでも、アメリカに亡命していた一部の弟子たちはアドラーの思想を再構築しようと試み、心理学の荒波の中に再びその灯をともしていきます。
ここから、アドラー心理学の“第二の誕生”が始まるのです。
ドライカースとアンスバッハーが築いた復興の礎
アドラーの弟子ルドルフ・ドライカースは、戦後のアメリカでアドラー心理学を実践的な形に再編成しました。
シカゴを拠点に、彼は積極的に講演活動を行い、家庭教育やカウンセリングにおける実践技法を多数開発します。
一方、ハインツ・アンスバッハーは、理論的な整理と再定義に尽力しました。
彼は、アドラーが残した膨大な著作と講演記録をもとに、全体論・目的論・共同体感覚といった核となる思想を明確に体系化していきました。
この「実践(ドライカース)」と「理論(アンスバッハー)」の2本柱によって、
アドラー心理学は戦後の混乱を超えて、現代でも学べる理論体系として再生されていきます。
第三世代の広がりとヨーロッパへの再輸出
ドライカースの活動はさらに広がり、弟子たちであるシャルマン、クリステンセン、モザックらが第三世代としてアドラー心理学を教育・医療・組織開発などへと応用し始めます。
中でも、娘のエヴァ・ドライカース・ファーガソンは、ICASSI(国際アドラー心理学サマーセミナー)を創設し、
ヨーロッパを中心にアドラー心理学を再び“逆輸入”する動きをけん引しました。
このセミナーは現在も毎年開催されており、世界中のアドレリアン(アドラー心理学実践者)たちの交流と学びの場となっています。
思想の影響と第四世代への展開
1950〜1990年代には、行動主義や認知主義の台頭がアドラー心理学にも影響を与え、
アンスバッハーやドライカースはこれらの潮流に合わせて表現や技法を変化させていきました。
さらに1990年代以降は、ポストモダンや構造主義の波が到来。
第四世代と呼ばれる現代のアドラー心理学者たちは、それぞれの思想的背景を取り入れながら、アドラー心理学の新たな展開を模索しています。
日本においては、野田俊作氏が構造主義的な視点からアドラー心理学を再定義。
その思想は「共同体感覚」を越えて「関係の構造」へと視点を広げ、多くの読者や臨床家に支持されました。
「嫌われる勇気」と現代的なブーム
そして2013年、岸見一郎氏と古賀史健氏による『嫌われる勇気』が社会現象とも言えるベストセラーとなり、
アドラー心理学の名前が日本国内外の一般層に広まりました。
また、岩井俊憲氏をはじめとする多くの実践家たちが、YouTubeや書籍、セミナーなど多様な形でアドラー心理学の価値を伝え続けています。
アドラーの名は、もはや専門家だけのものではありません。
「どう生きるか」「どう関わるか」に悩むすべての人にとって、アドラー心理学は大切な道標のひとつとなっているのです。
まとめ
アドラー心理学は、歴史に翻弄されながらも、さまざまな人物の手によって発展を続けてきました。
その魅力は、「一人ひとりの人生を尊重する哲学」であり、
どの時代にも通じる“変わらない人間理解”が根底にあるからです。
今後も新たな解釈や実践を通じて、アドラー心理学はさらに進化していくでしょう。
私たちが「人としてどう生きるか」を問い続ける限り、その価値が薄れることはありません。
※本記事で使用されている画像は、すべてミッドジャーニー(Midjourney)で生成されたイメージです。
ロゴ.png)